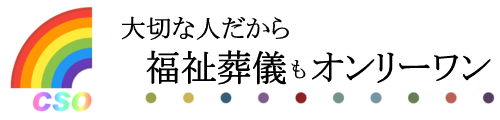生活保護受給者の葬儀はどうすればいいのか?
葬儀を執り行うにはお金がかかりますが、生活保護を受けていて経済的困窮している方の場合は、葬儀費用はどうすれば良いのでしょうか。
こちらでは、自治体が葬儀費用を負担する生活保護制度「葬祭扶助」と、葬祭扶助を利用して行う「生活保護葬葬」について解説いたします。
葬祭扶助とは
葬祭扶助とは、生活保護制度の一種で、葬儀を執り行うべき人が生活保護を受けているなど経済的に困窮し、葬儀費用が払えない人を対象に最低限の葬儀(直葬)を支給する制度です。
葬祭扶助を受けるには申請が必要で、審査後に許可された場合は自治体が最低限の葬儀費用を負担します。
葬祭扶助(生活保護法より抜粋)
生活保護法 第十八条
葬祭扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。
一 検案
二 死体の運搬
三 火葬又は埋葬
四 納骨その他葬祭のために必要なもの
2 左に掲げる場合において、その葬祭を行う者があるときは、その者に対して、前項各号の葬祭扶助を行うことができる。
一 被保護者が死亡した場合において、その者の葬祭を行う扶養義務者がないとき。
二 死者に対しその葬祭を行う扶養義務者がない場合において、その遺留した金品で、葬祭を行うに必要な費用を満たすことのできないとき。
葬祭扶助の葬儀とは
葬祭扶助の葬儀では、検案・死体の運搬・火葬又は埋葬・納骨その他葬祭のために必要となる費用が支給されます。
葬祭扶助では最低限の葬儀になることから、一般的なお葬式で行われる通夜・告別式の費用や、僧侶にお渡しするお布施、祭壇花などの費用は支給されません。
そのため、宗教儀礼やセレモニーを行わない「直葬」や「火葬式」といったシンプルな形式で行われます。
また葬祭扶助は、生活困窮で葬儀費用がまかなえない人に対しての救済措置として位置付けられており、葬儀費用を補うための制度ではありません。
そのため、費用を追加して華美な葬儀を行うことはできませんので注意して下さい。
葬祭扶助の支給対象
葬祭扶助の支給対象となるのは、次のとおりです。
①喪主が生活保護受給者の場合
②亡くなった方が生活保護受給者で遺留金が葬祭扶助支給額に達していない場合
・遺族も経済的に困窮していて葬儀の費用をまかなえない場合
・遺族以外の人が葬儀を手配する場合
・死者の葬祭を行う扶養義務者がないとき
※自治体によって基準が異なりますので、詳しくは福祉事務所のケースワーカーにご相談ください。